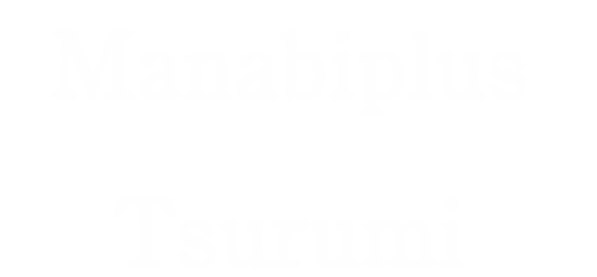地理もくじ
① 世界の姿
- 1) 三つの大洋のうち,最も大きい海。
- 太平洋
- 2) 三つの大洋のうち,南半球に占める割合が高い海。
- インド洋
- 3) 三つの大洋のうち,2番目に大きい海。
- 大西洋
- 4) 六つの大陸のうち,最も面積が大きい大陸。
- ユーラシア大陸
- 5) 六つの大陸のうち,地球上で日本の反対側に位置する大陸。
- 南アメリカ大陸
- 6) 六つの大陸のうち,最も面積が小さい大陸。
- オーストラリア大陸
- 7) 六つの大陸のうち,一年中雪と氷におおわれている大陸。
- 南極大陸
- 8) 世界の六つの州のうち,スイスの属する州。
- ヨーロッパ州
- 9) 世界の六つの州のうち,ケニアの属する州。
- アフリカ州
- 10) 世界の六つの州のうち,メキシコの属する州。
- 北アメリカ州
- 11) 世界の六つの州のうち,ニュージーランドの属する州。
- オセアニア州
- 12) アジア州の中で,ベトナムの属する地域。
- 東南アジア
- 13) アジア州の中で,スリランカの属する地域。
- 南アジア
- 14) アジア州の中で,ウズベキスタンの属する地域。
- 中央アジア
- 15) アジア州の中で,トルコの属する地域。
- 西アジア
- 16) アジア州の中で,モンゴルの属する地域。
- 東アジア
- 17) 周りを海に囲まれている国。
- 島国
- 18) 周りをすべて陸地に囲まれている国。
- 内陸国
- 19) 国と国との境界。
- 国境
- 20) 地球上の南北の位置を表す角度。
- 緯度
- 21) 約4万㎞の長さがある,緯度が0度の線。
- 赤道
- 22) 経度0度の基準となった旧グリニッジ天文台がある都市。
- ロンドン
- 23) 北緯90度の点。
- 北極点
- 24) 同じ経度を結んだ線。
- 経線
- 25) 経度0度の線。
- 本初子午線
- 26) 地球を,ほぼその形のまま小さくした模型。距離 ,面積,形,方位などを正しく表している。
- 地球儀
- 27) 地球儀のように情報を正しく一度に表せないが,持ち運びに便利で,世界全体を見渡せる図。用途に応じてさまざまな種類が作られている。
- 世界地図
② 日本の姿
- 1) その地域の標準時の基準となる経線。
- 標準時子午線
- 2) 地域間の標準時のずれ。
- 時差
- 3) 同じ標準時を使う地域。
- 等時帯
- 4) 経度180度を基準に引かれた,日付を調節する線。
- 日付変更線
- 5) その国の統治する権利がおよぶ,陸・海・空の範囲 。
- 領域
- 6) 領土沿岸から12海里以内の海(日本の場合)。
- 領海
- 7) 領土と領海上空の,大気圏内の空。
- 領空
- 8) 領海の外側で,領土沿岸から200海里以内の,沿岸国が水産資源や鉱産資源を管理する権利をもつ海。
- 排他的経済水域
- 9) 領海の外側の,海岸線から24海里までの範囲。沿岸の国が法律にもとづいた規制を行うことができる。
- 接続水域
- 10) 北海道の東の海上にある,日本の北端の島。
- 択捉島
- 11) 台湾の東側にある,日本の西端の島。
- 与那国島
- 12) 小笠原諸島の東方のはなれた海上にある,日本の東端の島。
- 南鳥島
- 13) 波による侵食を防ぐため護岸工事がほどこされた,日本の南端の島。
- 沖ノ鳥島
- 14) 択捉島を含め,日本固有の領土であるが,ロシアによって占拠されている島々。
- 北方領土
- 15) 島根県に属する日本固有の領土であるが,韓国に占拠されている島。
- 竹島
- 16) 沖縄県に属する日本固有の領土であるが,中国などが領有権を主張している島々。
- 尖閣諸島
- 17) 各都道府県が政治を行う中心となる,都道府県庁が置かれた都市。
- 都道府県庁所在地
- 18) 岩手県の県庁所在地。
- 盛岡市
- 19) 群馬県の県庁所在地。
- 前橋市
- 20) 三重県の県庁所在地。
- 津市
- 21) 愛媛県の県庁所在地。
- 松山市
③ 人々の生活と環境
- 1) 一年中気温が高い気候帯。
- 熱帯
- 2) 降水量が少ない気候帯。
- 乾燥帯
- 3) 温暖で四季の変化がはっきりしている気候帯。
- 温帯
- 4) 夏が短く,冬の寒さが厳しい気候帯。
- 亜寒帯(冷帯)
- 5) 気温が低く,樹木がほとんど育たない気候帯。
- 寒帯
- 6) 温帯のうち,1年を通して気温と降水量の変化が小さい気候。
- 西岸海洋性気候
- 7) 温帯のうち,冬に雨が降り,夏に乾燥する気候。
- 地中海性気候
- 8) 熱帯の地域で見られる,一時的な激しい風雨。
- スコール
- 9) 熱帯で見られる,一年中緑の葉がしげる森林。
- 熱帯林
- 10) 乾燥した地域で,わき水などにより水を得られる場所。
- オアシス
- 11) 家畜のえさとなる水や草を得るため,移動しながら行う牧畜。
- 遊牧
- 12) ロシア東部に広がる地域。大部分が亜寒帯(冷帯)に属する。
- シベリア
- 13) 一年中凍ったままの土壌。
- 永久凍土
- 14) 海面からはかった土地の高さのこと。高地ほど気温が低い。
- 標高
- 15) リャマなどの家畜を放し飼いにし,えさを自由に食べさせる飼育方法。
- 放牧
- 16) 日本や東南アジアなど雨の多い地域で栽培され,主食とされる穀物。
- 米
- 17) 比較的乾燥した地域を中心に栽培されている穀物。パンやめんの材料。
- 小麦
- 18) インドで生まれ,東南アジア・東アジアを中心に広まった宗教。
- 仏教
- 19) 西アジアで生まれ,ヨーロッパや南北アメリカを中心に広まった宗教。
- キリスト教
- 20) アラビア半島で生まれた宗教。豚肉や酒の飲食が禁止されている。
- イスラム教
- 21) おもにインドで信仰されている宗教。牛を神聖なものとしている。
- ヒンドゥー教
- 22) 日本で古くから信仰されている宗教。
- 神道
- 23) アラビア半島にある,イスラム教徒にとって最大の聖地。
- メッカ
- 24) インドの伝統的な身分制度。現在,これによる差別は禁じられている。
- カースト
④ アジア州①
- 1) イスラム教徒が多く,アジア州とヨーロッパ州にまたがっている国。首都はアンカラ。
- トルコ
- 2) 国土の多くを砂漠が占める,原油の埋蔵量が世界有数の国。首都はリヤド。
- サウジアラビア
- 3) ドバイなど7つの首長国からなる国。日本への原油輸出量が多い。
- アラブ首長国連邦
- 4) ヒンドゥー教徒が人口の約8割を占める国。首都はデリー。
- インド
- 5) イスラム教徒が多く,インダス文明の遺跡モヘンジョ゠ダロがある国。首都はイスラマバード。
- パキスタン
- 6) 東アジアの遊牧がさかんな内陸国。近年は定住化が進んでいる。首都はウランバートル。
- モンゴル
- 7) 人口14億人を超え,経済発展を遂げた東アジアの国の正式名称。
- 中華人民共和国
- 8) 携帯電話の生産がさかんな,日本の隣の国の正式名称。首都はソウル。
- 大韓民国
- 9) 多くの島々からなる国。イスラム教徒の人口は世界一。首都はジャカルタ。
- インドネシア
- 10) かつては原油や天然ゴムの輸出量が多かったが,工業化により機械類の輸出量が大きく増加した国。首都はクアラルンプール。
- マレーシア
- 11) 日本へのバナナの輸出量が多い国。首都はマニラ。
- フィリピン
- 12) 稲作がさかんで,米の輸出量が世界有数の国。首都はバンコク。
- タイ
- 13) かつて南北に分かれていた国。首都はハノイ。
- ベトナム
- 14) マレー半島の先端に位置し,貿易の中継点として経済発展してきた国。
- シンガポール
- 15) 郊外に世界遺産である万里の長城がある,中国の首都。
- ペキン(北京)
- 16) アジア東部の気候に影響を与え,夏と冬でふく向きが逆になる風。
- 季節風(モンスーン)
- 17) 1年の中で,特に降水量の多い時期や季節。
- 雨季
- 18) 1年の中で,特に降水量が少なく乾燥した時期や季節。
- 乾季
- 19) 畑地での農業。降水量の少ない地域を中心に,小麦などが栽培される。
- 畑作
- 20) 用水などによって,川や地下水から農地に水を引くこと。
- かんがい
- 21) 中国で人口増加を抑制するために行われていた政策。子どもの数を一夫婦あたり一人に制限していた。
- 一人っ子政策
- 22) 中国の沿海部で,外国企業を受け入れるためにさまざまな優遇制度が設けられた地域。
- 経済特区
- 23) 工業製品を大量に製造し,世界中に輸出している中国を表す言葉。
- 世界の工場
- 24) 国と国,もしくは人と人の間の著しい収入の差。中国では,沿海部と内陸部の人々の間に生じている。
- 経済格差
⑤ アジア州②
- 1) 乾燥した地域が広がる西アジアの半島。
- アラビア半島
- 2) ヨーロッパと中央アジアの州境にあり,原油や天然ガスが豊富に産出される塩湖。
- カスピ海
- 3) 沿岸で原油が大量に産出される,西アジアの湾。
- ペルシア湾
- 4) パキスタンを流れる,流域に古代文明が栄えた川。中流部で小麦などの栽培がさかん。
- インダス川
- 5) ヒンドゥー教で「聖なる川」とみなされる川。下流域で稲作がさかん。
- ガンジス川
- 6) インド半島の中央にある,綿花栽培がさかんな高原。
- デカン高原
- 7) 世界最高峰であるエベレスト山のある山脈。
- ヒマラヤ山脈
- 8) 中国南西部に広がる高原。
- チベット高原
- 9) 中国を流れる,流域で小麦や大豆などの栽培がさかんな川。
- 黄河
- 10) アジア州で最も長い,流域で稲や茶の栽培がさかんな川。
- 長江
- 11) 現在,1つの民族が2つの国家に分かれている,東アジアの半島。
- 朝鮮半島
- 12) 東南アジアのいくつかの国の国境であり,下流域で稲作がさかんな川。
- メコン川
- 13) 大部分がサバナ気候に属する,東南アジアの半島。
- インドシナ半島
- 14) インドシナ半島からのびている,おもに熱帯雨林気候に属する半島。
- マレー半島
- 15) インドネシアの首都ジャカルタの位置する島。
- ジャワ島
- 16) 海外に住み,現地の国籍をもつ中国系の人々。東南アジアやアメリカ合衆国で広く活躍している。
- 華人
- 17) 1年に2回,同じ耕地で同じ作物を栽培すること。
- 二期作
- 18) 東南アジアの国々が,企業の進出を促すために,工場や倉庫を計画的に建てた地域。
- 工業団地
- 19) 中心となる一つの地域に,人口と国の機関や大企業の本社などが集まること。
- 一極集中
- 20) 東南アジアの10か国で構成された,地域協力のための組織。
- 東南アジア諸国連合(ASEAN)
- 21) 電子機器や通信サービスの開発・販売など,情報通信に関わる最先端の技術を利用した産業。
- 情報通信技術(ICT)関連産業
- 22) 採掘された原油や天然ガスなどを,大量に長距離輸送するためにつくられた管状の施設。
- パイプライン
- 23) 原油を輸出している国々が,自国の利益を守るために1960年に結成した組織。西アジア・アフリカ州・南アメリカ州の産油国が加盟している。
- 石油輸出国機構(OPEC)
⑥ ヨーロッパ州
- 1) 世界で最初に近代工業が発展した国。首都はロンドン。
- イギリス
- 2) 福祉が充実している国。首都はコペンハーゲン。
- デンマーク
- 3) ヨーロッパ連合(EU)最大の農業国。首都はパリ。
- フランス
- 4) 自動車産業などがさかんな工業国。首都はベルリン。
- ドイツ
- 5) オレンジの栽培がさかんな国。首都はマドリード。
- スペイン
- 6) 干拓で国土を広げてきた歴史をもつ国。首都はアムステルダム。
- オランダ
- 7) かつて古代帝国が栄えた,ぶどうやオリーブの栽培がさかんな国。首都はローマ。
- イタリア
- 8) 世界で最も面積が大きい国。首都はモスクワ。
- ロシア(ロシア連邦)
- 9) オリンピック発祥の地である,観光業がさかんな国。首都はアテネ。
- ギリシャ
- 10) モンブラン山を最高峰とする,ヨーロッパ最大の山脈。
- アルプス山脈
- 11) ドイツやオランダなどをまたいで流れる国際河川。
- ライン川
- 12) 氷河がつくり出した細長い湾が続く,ヨーロッパ州北部の半島。高緯度地域では,夏に太陽が一日中沈まない「白夜」という現象が見られる。
- スカンディナビア半島
- 13) ヨーロッパ州とアフリカ大陸の間にある内海。
- 地中海
- 14) ヨーロッパ州とアジア州を分ける山脈。
- ウラル山脈
- 15) 氷河でけずられてできた谷に,海水が深く入りこんだ地形。
- フィヨルド
- 16) ヨーロッパ州の西側の海を流れる暖流。
- 北大西洋海流
- 17) 中緯度から高緯度に向かって,一年中,西から東へふく風。
- 偏西風
- 18) デンマークなどのヨーロッパ北西部で信仰する人が多い,キリスト教の宗派 。
- プロテスタント
- 19) イタリアなどのヨーロッパ南部で信仰する人が多い,キリスト教の宗派。
- カトリック
- 20) ロシアなどのヨーロッパ東部で信仰する人が多い,キリスト教の宗派。
- 正教会
- 21) イギリスやドイツで使われている言語の系統。
- ゲルマン系(ゲルマン系言語)
- 22) ヨーロッパ連合の多くの国で使われている共通通貨。
- ユーロ
- 23) 家畜の飼育と作物の栽培を組み合わせた農業。
- 混合農業
- 24) 乳牛ややぎを飼育し,チーズやバターなどの乳製品を生産する農業。
- 酪農
- 25) 乾燥する夏にぶどうやオリーブなどの果樹を栽培し,雨の多い冬に小麦などを栽培する農業。
- 地中海式農業
- 26) 航空機の生産など,最先端の高度な技術を基盤とした産業。
- 先端技術産業
⑦ アフリカ州
- 1) カカオ豆や原油の輸出額が大きい,アフリカ州西部の国。
- コートジボワール
- 2) コートジボワールの東に位置し,カカオ豆の輸出額が大きい国。
- ガーナ
- 3) アフリカ州で最も人口が多く,原油が豊富な国。
- ナイジェリア
- 4) 古代文明発祥の地の一つで,ピラミッドなどの世界的な観光名所をもつ国。
- エジプト
- 5) 茶の栽培がさかんな国。首都はナイロビ。
- ケニア
- 6) 輸出額に占める銅の割合が高い,アフリカ州南部の国。近年は,農業や観光業にも力を入れている。
- ザンビア
- 7) 金やプラチナなどが豊富に産出される,アフリカ州で最も工業が発展している国。
- 南アフリカ共和国
- 8) コーヒー豆の輸出額が大きく,国土の大部分が高原地帯にある,アフリカ州東部の国。
- エチオピア
- 9) タンザニアにある,アフリカ大陸で最も高い山。
- キリマンジャロ山
- 10) アフリカ大陸東部を流れる世界一長い川。
- ナイル川
- 11) アフリカ大陸北部に広がる世界最大の砂漠。
- サハラ砂漠
- 12) 沿岸部でカカオの栽培がさかんな,アフリカ大陸西部の湾。
- ギニア湾
- 13) アフリカ大陸中央部の熱帯林におおわれた盆地 。
- コンゴ盆地
- 14) アフリカ州で最も大きい島。
- マダガスカル島
- 15) 熱帯地方に見られる,低い木が点在する草原。
- サバナ
- 16) サハラ砂漠の南にある,わずかに植物が生えている地域。
- サヘル
- 17) おもに乾燥した地域で,土地が生産力の低い荒れ地に変わること。
- 砂漠化
- 18) ほかの国に支配された地域。かつて,アフリカ州のほとんどの国はヨーロッパ州の国々に支配されていた。
- 植民地
- 19) 自由をうばわれ,売買された人々。16世紀以後,アフリカ大陸の人々の多くが南北アメリカ大陸に強制的に送り込まれた。
- 奴隷
- 20) アフリカ諸国の問題解決をめざしてつくられた地域統合体。
- アフリカ連合(AU)
- 21) 原油などのエネルギー資源や,金属の材料となる鉱物の総称。
- 鉱産資源
- 22) 埋蔵量が少なく採取の難しい希少な金属。電子部品などに使われている。
- レアメタル
- 23) 特定の農産物や鉱産資源の輸出にたよった経済。
- モノカルチャー経済
- 24) おもに国際機関と協力して活動する,政府ではない組織。
- 非政府組織(NGO)
⑧ 北アメリカ州
- 1) 世界をリードする工業国で,日本とのつながりが深い,北アメリカ州の国の正式名称。
- アメリカ合衆国
- 2) 国土の大部分が亜寒帯(冷帯)に属する,北アメリカ州の国。
- カナダ
- 3) アメリカ合衆国の企業の工場が数多く進出している,北アメリカ州の国。スペイン語が公用語とされている。
- メキシコ
- 4) かつて,鉄鋼業の中心地として発展したアメリカ合衆国の都市。
- ピッツバーグ
- 5) アメリカ合衆国の首都。大統領官邸や議会議事堂がある。
- ワシントンD.C.
- 6) 世界の政治・経済の中心をになう,アメリカ合衆国最大の都市。
- ニューヨーク
- 7) 北アメリカ大陸の西部をつらぬく,けわしい山脈。
- ロッキー山脈
- 8) 北アメリカ大陸の中央平原を流れる,世界第4位の長さをもつ川。
- ミシシッピ川
- 9) 北アメリカ大陸東部の,比較的なだらかな山脈。
- アパラチア山脈
- 10) スペリオル湖,ミシガン湖など五つの湖の総称。
- 五大湖
- 11) カリブ海域に浮かぶ,熱帯に属する島々。世界的なリゾート地がある。
- 西インド諸島
- 12) ロッキー山脈の東に位置する高原状の大平原。大規模な小麦地帯。
- グレートプレーンズ
- 13) グレートプレーンズの東に広がる,たけの長い草原地帯。小麦や綿花の栽培がさかん。
- プレーリー
- 14) 北アメリカ大陸に住む先住民の人々。
- ネイティブアメリカン
- 15) ほかの国や地域に移住する人々。北アメリカ大陸には,ヨーロッパ州から多くの人々が移り住んできた。
- 移民
- 16) メキシコなどからアメリカ合衆国に移り住んできた,スペイン語を話す人々のこと。
- ヒスパニック
- 17) 各地の自然条件に適した農作物を栽培すること。
- 適地適作
- 18) 肥料・農薬の開発や,農作物の加工・販売など,農業にかかわる産業。
- アグリビジネス
- 19) アグリビジネスを行う企業の中でも,穀物の流通に特に大きな影響力をもつ大企業。
- 穀物メジャー
- 20) 1970年代以降に先端技術産業が発達した,アメリカ合衆国の北緯37度線より南の地域。
- サンベルト
- 21) アメリカ合衆国のカリフォルニア州にある,情報通信技術(ICT)関連企業が集まる地域。
- シリコンバレー
- 22) 地下深くにある岩の層から採取される,天然ガスの一つ。アメリカ合衆国に多く埋蔵されており,新しい資源として注目されている。
- シェールガス
- 23) いくつもの国にまたがって生産や販売を行う企業。
- 多国籍企業
- 24) 二酸化炭素などの温室効果ガスの増加によって,地球全体の気温が上昇している環境問題。
- 地球温暖化
⑨ 南アメリカ州
- 1) 南アメリカ州で面積と人口が最大の国。首都はブラジリア。
- ブラジル
- 2) 銅の生産量が世界一の国。首都はサンティアゴ。
- チリ
- 3) 広大な草原での牧畜がさかんな,南アメリカ州の国。
- アルゼンチン
- 4) アルゼンチンの首都。
- ブエノスアイレス
- 5) カーニバルで有名なブラジルの都市。
- リオデジャネイロ
- 6) 南アメリカ大陸の西部を縦断する標高6000m級の山脈。
- アンデス山脈
- 7) 南アメリカ大陸を流れる,世界最大の流域面積をもつ川。流域に熱帯林が広がる。
- アマゾン川
- 8) アルゼンチンに広がる草原地帯。小麦の栽培や牛の放牧がさかん。
- パンパ
- 9) その土地でもともと生活していた人々。
- 先住民
- 10) 草原や森を焼き,残った灰を肥料にして作物を栽培する農業。
- 焼畑農業
- 11) とうもろこしやさとうきびなど,おもに植物を原料とする燃料。
- バイオ燃料
- 12) 都市化が進む中で形成された,居住環境の悪い地域。
- スラム
⑩ オセアニア州
- 1) 一つの大陸を占める国。首都はキャンベラ。
- オーストラリア
- 2) 牧畜がさかんで,飼育されている羊の数が人口より多い国。首都はウェリントン。
- ニュージーランド
- 3) オーストラリアで最も人口が多い都市。
- シドニー
- 4) パラオやマーシャル諸島が属するオセアニア州の地域。
- ミクロネシア
- 5) ニューギニア島やフィジーが属するオセアニア州の地域。
- メラネシア
- 6) ハワイ諸島やクック諸島が属するオセアニア州の地域。
- ポリネシア
- 7) さまざまな民族や文化をたがいに尊重し合う社会。
- 多文化社会
- 8) オーストラリアに住む先住民。独自の美術様式をもつ。
- アボリジニ
- 9) ニュージーランドに住む先住民。伝統的なおどり,ハカで有名。
- マオリ
- 10) アジア太平洋の国と地域が参加する,経済協力のための枠組み。
- アジア太平洋経済協力(APEC)
⑪ 自然環境の特色
- 1) ヨーロッパから東南アジアまで山地や山脈が連なる造山帯。
- アルプス・ヒマラヤ造山帯
- 2) 日本列島も含まれる,太平洋を囲むように連なる造山帯。
- 環太平洋造山帯
- 3) 「日本の屋根」ともよばれる,中部地方にある3000m級の山々の総称。
- 日本アルプス
- 4) 日本列島の地形を大きく2つに分ける溝状の地形。日本アルプスの東に位置する。
- フォッサマグナ
- 5) 川が山地から平野や盆地へ流れ出るところにできた扇形の地形。
- 扇状地
- 6) 川が海や湖に注ぐところに,土砂が堆積してできた地形。
- 三角州
- 7) 山が海にしずんだり海面が上昇したりしてできた,出入りの多い海岸。
- リアス海岸
- 8) 海の底に見られる深い溝。
- 海溝
- 9) 陸地周辺にある,浅くゆるやかな海底。日本列島の近海に広がる。
- 大陸棚
- 10) 本州の太平洋側を北上する暖流。
- 黒潮(日本海流)
- 11) 北海道の北方にある千島列島に沿って,太平洋を南下する寒流。
- 親潮(千島海流)
- 12) 黒潮(日本海流)の支流で,沖縄県の西を通り,日本海を北上する暖流。
- 対馬海流
- 13) 季節でふく向きが変わる風。日本では夏は南東から,冬は北西からふく。
- 季節風
- 14) 日本の気候区分のうち,北西からの季節風の影響で冬に雪が多く降る気候。
- 日本海側の気候
- 15) 日本の気候区分のうち,南東からの季節風の影響で夏に雨が多く降る気候。
- 太平洋側の気候
- 16) 水や砂の多い地面が,地震などの振動によって液体のようになる現象。
- 液状化
- 17) 台風や強い低気圧の影響で,海面が異常に高くなる現象。
- 高潮
- 18) 大雨で山がくずれ,水と土砂や石が激しく流れ出す現象。
- 土石流
- 19) 災害時に起こりうる被害をできる限り少なくしようとする考え方。
- 減災
- 20) 災害時の,国や都道府県,市町村などによる救助・復旧活動などの支援。
- 公助
- 21) 災害の被害が予測される範囲や,避難経路・避難場所を示した地図。
- ハザードマップ
⑫ 人口の特色
- 1) 東京・名古屋・大阪を中心に形成された3つの都市圏の総称。
- 三大都市圏
- 2) 人口が極端に集中した状態。交通渋滞などの都市問題が起こりやすい。
- 過密
- 3) 出生率が下がって子どもの数が減り,高齢者の割合が高くなった社会。
- 少子高齢社会
- 4) 国や地域の人口構成を,年齢と性別に分けて表したグラフ。
- 人口ピラミッド
⑬ 資源・産業の特色
- 1) 原油などの,エネルギー資源や工業の原料となる鉱物の総称。
- 鉱産資源
- 2) 水資源を利用した発電。ダムを利用するため,山間部に多い。
- 水力発電
- 3) 原油・石炭・天然ガスなどを燃料として利用した発電。
- 火力発電
- 4) ウランが核分裂するときに発生した熱を利用した発電。
- 原子力発電
- 5) 二酸化炭素の排出などが原因で,地球規模で気温が上昇すること。
- 地球温暖化
- 6) 太陽光や風力など,自然環境の中でくり返し生成できるエネルギー。持続可能な社会の実現のため,利用に期待が高まっている。
- 再生可能エネルギー
- 7) 電子部品などに使われ,埋蔵量が少ないためにリサイクルも行われている希少な金属の総称。
- レアメタル
- 8) 日本の耕地の半分以上を占め,全国各地で行われている農業。東北地方の日本海側や,北陸の平野部などでとくにさかん。
- 稲作
- 9) 国内で消費される食料のうち,国内で生産されたものの占める割合。
- 食料自給率
- 10) 沿岸から離れた沖合で行う漁業。遠洋漁業とともに漁獲量が減少。
- 沖合漁業
- 11) 繊維工業・食品工業などの,比較的軽量な製品を生産する工業。
- 軽工業
- 12) 機械工業などの比較的重量のある製品を生産する工業と,石油化学工業などの化学製品を生産する工業の総称。
- 重化学工業
- 13) コンピュータの生産など,最先端の高度な技術を基盤とした産業。
- 先端技術産業(ハイテク産業)
- 14) 関東沿岸部から九州北部にかけて,帯状に連なる臨海工業地域。
- 太平洋ベルト
- 15) 輸入した原料を加工し,製品を輸出する貿易。
- 加工貿易
- 16) 国家間の貿易により国内の産業や社会に問題が生じること。
- 貿易摩擦
- 17) 企業が生産拠点を海外に移すことで,国内の産業が衰退すること。
- 産業の空洞化
- 18) 産業を3種類に分類したうち,自然から生活に必要なものを得る産業。
- 第1次産業
- 19) 産業を3種類に分類したうち,原材料を加工する産業。鉱工業など。
- 第2次産業
- 20) 第3次産業のうち,小売業など,ものの売買により利益を得る産業。
- 商業
- 21) 第3次産業のうち,情報,医療など形のないものを提供する産業。
- サービス業
- 22) パソコンやインターネットなど,情報や通信にかかわる技術。利用できる人とできない人との間に,情報格差が生まれている。
- 情報通信技術(ICT)
⑭ 地域間の結びつきの特色
- 1) 新幹線・高速道路・航空路線など,高速の移動手段によるネットワーク。
- 高速交通網
- 2) 通信ケーブルや通信衛星,情報通信機器を通して,世界中の人々と情報をやりとりできるように整備されたネットワーク。
- 高速通信網
- 3) ある地域を共通点にもとづいて,いくつかのまとまりに区分すること。
- 地域区分
⑮ 九州地方
- 1) 九州の北部に連なる山地。
- 筑紫山地
- 2) 九州の中央部に位置する山地。
- 九州山地
- 3) 佐賀県南部にある,日本最大の干潟をもつ湾。
- 有明海
- 4) 熊本県にある火山。日本ジオパークに認定されている。
- 阿蘇山
- 5) 長崎県にある,1990年代に大きな噴火を起こした火山。
- 雲仙岳(普賢岳)
- 6) もとは島だったが,1914年の噴火により対岸の大隅半島と地続きになった火山。
- 桜島(御岳)
- 7) 佐賀県と福岡県にまたがる,稲作がさかんな平野。
- 筑紫平野
- 8) 九州地方南部にある,ピーマンなどの野菜の栽培がさかんな平野。
- 宮崎平野
- 9) 鹿児島県にある,貴重な自然が残され,1993年に世界遺産に登録された島。
- 屋久島
- 10) 屋久島や,鹿児島県・沖縄県の島を含む,九州南方の亜熱帯の島々の総称。
- 南西諸島
- 11) 九州地方最大の都市。古くから大陸との交流がさかんだった。
- 福岡市
- 12) 火山の火口が爆発によってくずれたり,侵食されたりしてできた,くぼんだ地形。阿蘇山に世界最大級のものがある。
- カルデラ
- 13) 東アジア特有の,毎年6月頃に,くもりや雨が多くなる期間。
- 梅雨
- 14) 夏から秋にかけて日本列島を通過する大型の低気圧。九州地方は通り道になりやすく,しばしば洪水や土砂災害などの被害を受ける。
- 台風
- 15) 地中で温められた水がわき出たもの。火山の多い地域でよく見られ,大分県別府市などでは,観光資源になっている。
- 温泉
- 16) 火山活動で生じる地熱で温められてできた蒸気を利用する発電所。
- 地熱発電所
- 17) 九州南部に広がる,火山噴出物が降り積もってできた水はけのよい台地。
- シラス台地
- 18) 九州では南部でさかんな,肉や乳などを得るために牛や豚,鶏などの家畜を飼育する産業。
- 畜産
- 19) 一年に2 回,同じ耕地で異なる種類の作物を栽培すること。
- 二毛作
- 20) 温暖な気候を生かし,ほかの地域よりも出荷時期を早める栽培方法。
- 促成栽培
- 21) 九州北部の工業地帯。鉄鋼業で発展し,現在では自動車工業がさかん。
- 北九州工業地帯
- 22) 人間の活動によって起こる,大気汚染・水質汚濁などの,健康や生活にかかわる被害。
- 公害
- 23) 小型で軽量の電子回路。多くの電気製品に組みこまれている。
- IC(集積回路)
- 24) サンゴの死骸などが海面近くまで積み上がってできた地形。
- サンゴ礁
⑯ 中国・四国地方
- 1) 中国地方をまたぐなだらかな山地。
- 中国山地
- 2) 四国地方を東西にのびる険しい山地。
- 四国山地
- 3) 四国地方最長の川。
- 四万十川
- 4) 流域面積が四国地方最大の川。
- 吉野川
- 5) 中国地方と四国地方にはさまれた,日本最大の内海。
- 瀬戸内海
- 6) 香川県の大部分に広がる平野。
- 讃岐平野
- 7) 太平洋に面した四国南部の平野。なすやピーマンの栽培がさかん。
- 高知平野
- 8) 鳥取県にある,日本有数の大きさの砂丘。らっきょうの栽培がさかん。
- 鳥取砂丘
- 9) 中国・四国地方最大の都市。
- 広島市
- 10) 中国山地より北の日本海側の地域。季節風の影響で冬の降雪量が多い。
- 山陰
- 11) 中国山地と四国山地にはさまれた地域。年間を通して降水量が少なく温暖。
- 瀬戸内
- 12) 四国山地より南の太平洋側の地域。季節風の影響で夏の降水量が多い。
- 南四国
- 13) 降水量の少ない瀬戸内で多く見られる,かんがい用の水をたくわえる池。
- ため池
- 14) 中国山地を東西につらぬく高速道路。
- 中国自動車道
- 15) 島根県と広島県を結ぶ高速道路。これの開通により,山陰・瀬戸内間の移動が容易になった。
- 浜田自動車道
- 16) 本州と四国を結ぶ3つの橋・ルートの総称。
- 本州四国連絡橋
- 17) 本州四国連絡橋のうち,岡山県倉敷市と香川県坂出市を結ぶ橋。1988年開通。
- 瀬戸大橋
- 18) 本州四国連絡橋のうち,本州と淡路島を結ぶ橋。1998年開通。
- 明石海峡大橋
- 19) 本州四国連絡橋のうち,四国と淡路島を結ぶ橋。1985年開通。
- 大鳴門橋
- 20) 瀬戸内海の沿岸に広がる工業地域。石油化学工業などの重化学工業が発達。
- 瀬戸内工業地域
- 21) 原油・石油製品に関連する大規模な工場群。効率のよい生産のため,関連工場が集められている。
- 石油化学コンビナート
- 22) 社会活動の維持が困難になるほど,人口が大幅に減少すること。
- 過疎(化)
- 23) 市町村を活性化させるため,自然や伝統・文化を生かした観光の目玉や地域の特色をつくろうとする取り組み。
- 地域おこし
- 24) 島根県にある世界遺産。銀を採掘したあとや,積み出しを行った港などが現在も残っている。
- 石見銀山
⑰ 近畿地方
- 1) 大阪府や兵庫県の大きな都市が位置する平野。
- 大阪平野
- 2) 古代から多くの都がおかれた京都府の盆地。
- 京都盆地
- 3) 奈良県北部に位置する盆地。
- 奈良盆地
- 4) たまねぎの生産がさかんな本州と四国のあいだの島。兵庫県に属する。
- 淡路島
- 5) 京都府北部にまたがる高地。
- 丹波高地
- 6) 真珠の養殖がさかんな,リアス海岸をもつ半島。三重県に属する。
- 志摩半島
- 7) 本州の太平洋側に突き出た,和歌山県・奈良県・三重県にまたがる半島。季節風の影響で夏の降水量が多い。
- 紀伊半島
- 8) リアス海岸をもつ,京都府北東部から福井県西部にかけての湾。
- 若狭湾
- 9) 近畿地方にある,温暖で降水量が多く,古くから林業がさかんな山地。
- 紀伊山地
- 10) 近畿地方の臨海部で工業地帯が広がる湾。
- 大阪湾
- 11) 滋賀県にある日本最大の湖。水運に利用されていた。
- 琵琶湖
- 12) 琵琶湖を水源とし大阪湾に注ぐ川の,大阪府を流れる範囲でのよび方。
- 淀川
- 13) 日本の標準時の基準となる東経135度に位置する都市。
- 明石市
- 14) 1995年に発生した兵庫県南部地震によって,兵庫県・大阪府を中心に大きな被害をもたらした大震災。
- 阪神・淡路大震災
- 15) 京都・大阪・神戸とその周辺地域の結び付きにより形成された大都市圏。
- 京阪神大都市圏
- 16) 大都市の過密を解消するために,郊外を開発してつくられた新しい町。
- ニュータウン
- 17) プランクトンの大量発生で,海や湖の水面が赤く染まる現象。
- 赤潮
- 18) 江戸時代,大阪が商業の中心であったことを指してよばれた名称。
- 天下の台所
- 19) 大阪府・兵庫県を中心とした工業地帯。
- 阪神工業地帯
- 20) 地下水などを大量にくみ上げたことにより土地が沈んでしまう現象。
- 地盤沈下
- 21) 阪神工業地帯の内陸部に多い,大企業に比べて小規模な企業。
- 中小企業
- 22) 人類共通の遺産として国際的に保護することを目的に,ユネスコにより登録された自然・建築物など。
- 世界遺産
- 23) 京都の西陣織や奈良の奈良墨など,その地域で受け継がれてきた原材料や技術を用いて現在もつくられている手工芸品。
- 伝統的工芸品
- 24) 土砂災害や地球温暖化を防ぐなど,環境保全の役割をもつ林。
- 環境林
⑱ 中部地方
- 1) 日本アルプスの最も北に位置する山脈。
- 飛驒山脈
- 2) 日本アルプスの中央に位置する山脈。
- 木曽山脈
- 3) 日本アルプスの最も南に位置する山脈。
- 赤石山脈
- 4) 木曽山脈の西側を流れ,伊勢湾に注ぐ川。下流で「輪中」が見られる。
- 木曽川
- 5) 中部地方にある,日本で最も長い川。
- 信濃川
- 6) 山梨県と静岡県の県境にある,日本の最高峰。
- 富士山
- 7) 名古屋市が位置する,中部地方最大の平野。
- 濃尾平野
- 8) ももやぶどうなど,果樹栽培がさかんな山梨県の盆地。
- 甲府盆地
- 9) 稲作がさかんで,日本有数の水田地帯がある新潟県の平野。
- 越後平野
- 10) 中部地方の太平洋側の地域。冬は晴天が続き,乾燥する。
- 東海
- 11) 中部地方の日本海側の地域。季節風の影響で冬の積雪量は世界有数。
- 北陸
- 12) 中部地方の内陸の地域。標高が高く,冬の寒さが厳しい。
- 中央高地
- 13) 名古屋市を中心とした工業地帯。自動車工業などの機械工業がさかん。
- 中京工業地帯
- 14) 名古屋市とその周辺の県や都市の結び付きにより形成された大都市圏。
- 名古屋大都市圏
- 15) 静岡県沿岸部に広がる工業地域。二輪車や紙製品の生産がさかん。
- 東海工業地域
- 16) 作物の成長を遅らせ,ほかの地域と出荷時期をずらす栽培方法。渥美半島での菊の電照栽培,中央高地でのレタス・キャベツの栽培など。
- 抑制栽培
- 17) 花や野菜を栽培する園芸農業のうち,温室やビニールハウスなどを利用するもの。東海でさかん。
- 施設園芸農業
- 18) 沿岸から遠く離れた海域で行う漁業。焼津港はこの漁業の基地。
- 遠洋漁業
- 19) 夏でも冷涼な高原地帯で栽培される,レタス・キャベツなどの野菜。
- 高原野菜
- 20) 高度な加工技術を用いて,時計やカメラなどをつくる工業。戦後,諏訪盆地では,製糸業にかわりさかんになった。
- 精密機械工業
- 21) ICや電子部品などをつくる工業。中央高地の高速道路沿いに工場が進出。
- 電気機械工業
- 22) 特定の産地や品種を指定し,ブランドとして商品化した高品質の米。
- 銘柄米
- 23) 同じ耕地で,年に一度, 1 種類だけ農作物を栽培すること。
- 単作
- 24) 地域で産出された原材料を活用するなどして,地域と密接に結びついた産業。
- 地場産業
⑲ 関東地方
- 1) 関東地方の大部分が含まれる,日本最大の平野。
- 関東平野
- 2) 中部地方と関東地方の境となる山地。関東地方の重要な水源の1つでもある。
- 関東山地
- 3) 千葉県にある温暖な気候の半島。花や野菜の栽培がさかん。
- 房総半島
- 4) 房総半島と三浦半島に囲まれた,沿岸部に埋立地の多い湾。
- 東京湾
- 5) 流域面積が日本最大で,長さは日本第2位の川。関東地方にある。
- 利根川
- 6) 東京都心から約1000㎞離れた,亜熱帯の気候に属する島々。世界遺産に登録されている。
- 小笠原諸島
- 7) 関東平野の大部分をおおう,火山灰が降り積もってできた赤土。
- 関東ローム
- 8) 都市化によるコンクリート面の増加や樹木の不足などが原因で,都市中心部の気温が周囲と比べて高くなる現象。
- ヒートアイランド現象
- 9) 日本における東京のように,その国の政治の最高機関がある都市。
- 首都
- 10) ある地域における,夜間の時間帯の人口。実際に居住している人口。
- 夜間人口
- 11) ある地域における,昼間の時間帯の人口。
- 昼間人口
- 12) 新宿・池袋のような,都心のもつ機能の一部をになう地区。
- 副都心
- 13) 東京都にある,国内線の中心となっている空港。
- 東京国際空港(羽田空港)
- 14) 日本の国際線の中心で,貿易額が日本最大である千葉県の空港。
- 成田国際空港
- 15) 東京都とその周辺の県や都市の結び付きによって形成された大都市圏。日本の約4分の1の人口が集中して過密になっている地域。
- 東京大都市圏
- 16) 人口や交通量の変化などに対応するため,市街地を開発しなおすこと。
- 再開発
- 17) 人口50万人以上で,国に特別に指定された市。府や県なみの権限をもつ。
- 政令指定都市
- 18) 電子機器や通信サービスの開発・販売など,情報通信に関わる最先端の技術を利用した産業。
- 情報通信技術(ICT)関連産業
- 19) 東京都の臨海部を中心に広がる,日本有数の工業地帯。
- 京浜工業地帯
- 20) 千葉県側の東京湾岸を中心に広がる工業地域。化学工業がさかん。
- 京葉工業地域
- 21) 関東地方の内陸部に広がる,工業団地の多い工業地域。
- 北関東工業地域
- 22) 大きな都市などの大消費地の近くで行われる農業。
- 近郊農業
- 23) 一度大都市に移住した人が,出身地にもどり生活すること。
- Uターン
- 24) Uターンに対し,大都市出身の人が出身地以外の地域に移住し生活すること。
- Iターン
⑳ 東北地方
- 1) 青森県北西部にある,りんごの栽培がさかんな平野。
- 津軽平野
- 2) 秋田県の日本海側にある,稲作がさかんな平野。
- 秋田平野
- 3) 山形県の日本海側にある,稲作がさかんな平野。
- 庄内平野
- 4) さくらんぼなど,果樹栽培がさかんな山形県の盆地。
- 山形盆地
- 5) 東北地方最大の平野。
- 仙台平野
- 6) 「なまはげ」の行事が残っていることで有名な,秋田県の半島。
- 男鹿半島
- 7) 東北地方にある,ぶなの原生林が残る,世界遺産に登録されている山地。
- 白神山地
- 8) 東北地方を日本海側と太平洋側に分ける大きな山脈。
- 奥羽山脈
- 9) 日本海側で南北にのびる積雪の多い山地。奥羽山脈の西側。
- 出羽山地
- 10) 太平洋側で南北にのびる高地。奥羽山脈の東側。
- 北上高地
- 11) 東北地方最長の川。
- 北上川
- 12) 山形県を流れ,日本海へ注ぐ急流の川。
- 最上川
- 13) 青森県から宮城県にかけて続く,南部にリアス海岸をもつ海岸。
- 三陸海岸
- 14) 本州と北海道の間にある海峡。青函トンネルが通っている。
- 津軽海峡
- 15) 宮城県の県庁所在地。東北地方唯一の政令指定都市であり,この都市を中心に都市圏が形成されている。
- 仙台市
- 16) 秋田市に伝わる,米の豊作をいのる祭り。毎年夏に行われる。
- 秋田竿燈まつり
- 17) 青森市で行われる,巨大な人形に明かりを灯して町を練り歩く祭り。
- 青森ねぶた祭
- 18) 秋田竿燈まつりや青森ねぶた祭のように,人々の生活や文化と深く結び付きながら現代まで受け継がれてきた行事。
- 伝統行事
- 19) 東北地方の太平洋側で,夏に北東からふく冷たい風。ふくと日照時間が不足して,冷夏になることがある。
- やませ
- 20) やませの影響で夏でも気温が上がらず,農作物の生育に被害がおよぶこと。
- 冷害
- 21) 国内の米の消費量が減り,余るようになったため,政府が行った米の生産量を減らす政策。ほかの作物への転作や,銘柄米の開発が進んだ。
- 減反政策
- 22) 暖流と寒流がぶつかる場所。栄養豊富でたくさんの魚が集まる。
- 潮目(潮境)
- 23) 企業の進出を促すために,工場や倉庫を計画的に建てた地域。
- 工業団地
- 24) 岩手県盛岡市などで生産されている伝統的工芸品の鉄器。
- 南部鉄器
㉑ 北海道地方
- 1) 北海道北部の山地。
- 北見山地
- 2) 北海道南部を南北に走る険しい山脈。
- 日高山脈
- 3) 北海道西部にある稲作がさかんな平野。減反政策で転作が進む。
- 石狩平野
- 4) 日高山脈の東側にある畑作がさかんな平野。
- 十勝平野
- 5) 北見山地の南西にある稲作がさかんな盆地。
- 上川盆地
- 6) 豊かな自然が残り世界遺産に登録されている,オホーツク海に突き出した半島。
- 知床半島
- 7) 北方領土で2番目に大きい島。
- 国後島
- 8) 北方領土で最も大きい,日本最北端の島。
- 択捉島
- 9) 北海道東部の台地。夏でもすずしく,乳牛の飼育が行われている。
- 根釧台地
- 10) 北海道で最も長い川。
- 石狩川
- 11) 冬に沿岸で流氷が見られる,北海道の北東にある海。
- オホーツク海
- 12) 1943~45年の噴火で昭和新山を形成した火山。洞爺湖の南に位置する。
- 有珠山
- 13) 北海道のほとんどが属する気候帯。夏が短く冬の寒さが厳しい。
- 亜寒帯(冷帯)
- 14) 北海道の太平洋沿岸地域で,夏の南東の季節風と寒流の親潮によって発生する現象。
- 濃霧
- 15) 雪の多い地域において,生活に役立つように雪を有効活用すること。
- 利雪
- 16) 寒冷な気候のために分解されなかった枯れた植物が,沼地などに長い間積もってできた土地。
- 泥炭地
- 17) 明治時代,北海道の開拓のために置かれた役所。
- 開拓使
- 18) 開拓使が設置され,北海道の警備と開拓を目的として移住した人々。
- 屯田兵
- 19) 地力を保つため,1 つの耕地で数種類の作物を年ごとに栽培すること。
- 輪作
- 20) 乳牛を飼育して生乳や乳製品を生産する農業。根釧台地でさかん。
- 酪農
- 21) かつて北海道でさかんだった,ロシアなど北方の外国近海で行う漁業。
- 北洋漁業
- 22) いけすなどの囲いの中で人工的に魚介類を育ててとる漁業。
- 養殖業
- 23) 稚魚をある程度まで育てて放流し,成長してから捕獲する漁業。
- 栽培漁業
- 24) 生態系を乱さず保全することと,それを観察・体験して楽しむことを両立する観光のあり方。
- エコツーリズム
㉒ 地域の在り方"
- 1) 環境保護と開発を両立させた,将来の世代に継承できる社会。
- 持続可能な社会