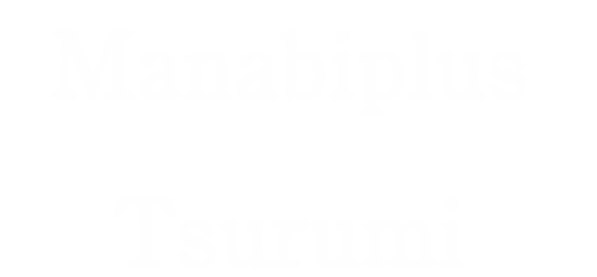公民もくじ
①現代社会と私たち
- 1) 人・もの・お金・情報などが国境をこえ,世界に広がっていくこと。
- グローバル化(世界の一体化)
- 2) 生活のさまざまな場面で,情報が大きな役割を果たすようになること。
- 情報化
- 3) 子どもの数が減少し,人口にしめる高齢者の割合が増加した社会。
- 少子高齢社会
- 4) 将来と現在の世代の両方が幸福でいられる社会。
- 持続可能な社会
- 5) 長い歴史の中で人々に受けつがれてきた文化。
- 伝統文化
- 6) 昔から受けつがれてきた文化を財産として保存し活用するための法律。
- 文化財保護法
- 7) さまざまな文化をもつ人々がともに生活していくこと。
- 多文化共生
- 8) 時間,お金,労力などの無駄を省くという意味で使う考え方。
- 効率
- 9) 特定の人が不当な扱いを受けることがないという意味で使う考え方。
- 公正
- 10) みんなが納得し,反対者がいない案を採用する決まりの決め方。
- 全会一致
- 11) 賛成者がより多い案を採用する決まりの決め方。
- 多数決
②個人の尊重と日本国憲法
- 1) 1776年にアメリカで出された,イギリスからの独立を宣言した文書。
- アメリカ独立宣言
- 2) 1789年にフランスで出された,「人は生まれながら,自由で平等な権利をもつ」という内容が盛りこまれた宣言。
- フランス人権宣言(人間および市民の権利の宣言)
- 3) 1919年にドイツで制定された,社会権を保障した憲法。
- ワイマール憲法
- 4) 1889年に日本で発布された,主権者を天皇と定めた憲法。
- 大日本帝国憲法
- 5) 『法の精神』で,三権分立を説いたフランスの思想家。
- モンテスキュー
- 6) 国民の権利を守るために,憲法で政治権力を制限するという考え方。
- 立憲主義
- 7) 国の政治は国民が決定権をもち,国民の意思に従い行うという原理。
- 国民主権
- 8) 戦争を放棄し,恒久の平和のために努力するという原理。
- 平和主義
- 9) 個人を尊重し,人としての権利を保障するという原理。
- 基本的人権の尊重
- 10) 憲法改正の発議に必要な,衆議院・参議院それぞれの総議員にしめる賛成の割合。(分数を使って答えなさい。)
- 3分の2以上
- 11) 憲法改正の手続きにおいて行われる,国民による投票のこと。
- 国民投票
- 12) 日本が他国から攻撃された時の,アメリカとの共同防衛を定めた条約。
- 日米安全保障条約(日米安保条約)
- 13) 核兵器を「持たず,作らず,持ちこませず」という原則。
- 非核三原則
- 14) 1989年に国連で採択された,子どもの人権を守ることを目的とした条約。
- 子ども(児童)の権利条約
- 15) 基本的人権のうち,すべての人が平等に扱われる権利。
- 平等権
- 16) 日本国憲法で保障された自由権のうち,思想・良心の自由や信教の自由をふくむ自由のこと。
- 精神の自由
- 17) 日本国憲法で保障された自由権のうち,法定手続きの保障や拷問の禁止をふくむ自由のこと。
- 身体の自由
- 18) 日本国憲法で保障された自由権のうち,居住・移転の自由や財産権の保障をふくむ自由のこと。
- 経済活動の自由
- 19) 基本的人権のうち,教育を受ける権利や勤労の権利など,人間としての豊かな生活を保障する権利。
- 社会権
- 20) 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利。
- 生存権
- 21) 基本的人権のうち,選挙権や被選挙権など,政治に参加する権利。
- 参政権
- 22) 日本国憲法で保障された請求権のうち,無罪判決を受けた人が国に補償を求める権利。
- 刑事補償請求権
- 23) 精神の自由のうち,自分の考えを言ったり,考えをまとめた本を出版したりする自由のこと。
- 表現の自由
- 24) 経済活動の自由のうち,好きな職業を選べる自由のこと。
- 職業選択の自由
- 25) 雇用における男女の平等をめざした法律。
- 男女雇用機会均等法
- 26) 男女が対等な立場で,社会のさまざまな活動に参加し,利益や責任を分かち合う社会の実現をめざした法律。
- 男女共同参画社会基本法
- 27) 体の不自由な人などにとっての社会の中の障壁を取り除くという考え。
- バリアフリー
- 28) 労働者が団結して行動するために,労働組合をつくる権利。
- 団結権
- 29) 労働組合が労働条件の改善を求めて,使用者と交渉する権利。
- 団体交渉権
- 30) 要求の実現のため,労働者がストライキなどをする権利。
- 団体行動権
- 31) 社会生活において,ある人の人権を保障するために,他の人の人権保障を制約する場合があるという人権保障の限界のこと。
- 公共の福祉
- 32) 国民の三大義務の1つで,教育に関わる義務。
- (子どもに)普通教育を受けさせる義務
- 33) 国民の三大義務の1つで,働くことに関わる義務。
- 勤労の義務
- 34) 国民の三大義務の1つで,税に関わる義務。
- 納税の義務
- 35) 開発の際,環境への影響を事前に調査すること。
- 環境アセスメント(環境影響評価)
- 36) 自分の生き方や生活のしかたを,自分の意思で自由に決める権利。
- 自己決定権
- 37) 新しい人権の1つで,政治にかかわる情報を入手する権利。
- 知る権利
- 38) 行政機関がもつ情報の開示を請求できる制度。
- 情報公開制度
- 39) 新しい人権の1つで,個人の生活や情報を公開されない権利。
- プライバシーの権利
- 40) 情報を管理する者に個人情報の慎重な管理を義務付けた制度。
- 個人情報保護制度
- 41) 1948年に国連総会で採択された,各国の人権保障の手本とされる宣言。法的拘束力はない。
- 世界人権宣言
- 42) 国境をこえて社会貢献を行う民間団体。
- NGO(非政府組織)
③現代の民主政治と社会
- 1) 国民や住民が代表者を選挙し,代表者が議会で話し合う方法で行われる政治のしくみ。
- 間接民主制(議会制民主主義)
- 2) 一定年齢以上のすべての国民に選挙権を保障する原則。
- 普通選挙
- 3) 1人につき1票の投票権があるという原則。
- 平等選挙
- 4) 有権者が代表を直接選ぶという原則。
- 直接選挙
- 5) 無記名で投票するという原則。
- 秘密選挙
- 6) 1つの選挙区において,1人を選ぶ選挙制度。
- 小選挙区制
- 7) 政党の得票数に応じて各政党へ議席を配分する選挙制度。
- 比例代表制
- 8) 衆議院議員の選挙制度。
- 小選挙区比例代表並立制
- 9) 政権を担当する政党。
- 与党
- 10) 政権を担当せず,内閣を監視・批判する政党。
- 野党
- 11) 複数の政党が協力して内閣を組織する政権。
- 連立政権(連立内閣)
- 12) 各政党が選挙の際に発表する,政権を担当した場合に実施する政策や数値目標,達成期限,財源などを明らかにしたもの。
- 政権公約
- 13) 多くの人のまとまった意見。
- 世論
- 14) 国の唯一の立法機関で,国権の最高機関。
- 国会
- 15) 任期が4年で,解散がある議院。
- 衆議院
- 16) 任期が6年で,解散がなく,3年ごとに半数が改選される議院。
- 参議院
- 17) 予算の先議権や議決の優先権など,衆議院を優先させるしくみ。
- 衆議院の優越
- 18) 法律案の議決で,衆議院と参議院の議決が異なった場合,衆議院で再可決するために必要な出席議員の賛成数。(分数で答えなさい。)
- 3分の2以上
- 19) 参議院議員の被選挙権年齢。
- 30歳以上
- 20) 両議院が異なる議決をした場合に開かれることがある協議会。
- 両院協議会
- 21) 毎年1回,1月に召集される国会。会期は150日間で延長もできる。
- 常会(通常国会)
- 22) 内閣の要求や一方の議院の総議員の4分の1以上の要求で召集される国会。
- 臨時会(臨時国会)
- 23) 衆議院の解散後の総選挙から30日以内に召集される国会。
- 特別会(特別国会)
- 24) 国会において,本会議で審議を行う前に話し合う,少数の議員が参加する会。
- 委員会
- 25) 衆議院と参議院がもつ,政治の状況を調査する権限。
- 国政調査権
- 26) 国会が設置する,裁判官を辞めさせるかどうかを決める裁判所。
- (裁判官)弾劾裁判所
- 27) 国会によって国会議員の中から指名される,内閣の長。
- 内閣総理大臣(首相)
- 28) 内閣総理大臣によって任命される,内閣の構成員。
- 国務大臣
- 29) 内閣の仕事を信頼できない時に,衆議院が行う決議。
- 内閣不信任の決議(不信任の決議)
- 30) 内閣不信任の決議が可決した場合,内閣が総辞職の他に行うことができる,衆議院の全議員の地位を失わせること。
- 解散
- 31) 内閣が国会の選んだ内閣総理大臣を中心に組織され,国会に対して連帯して責任を負うというしくみ。
- 議院内閣制
- 32) 内閣が政治の運営のことを全会一致で決めるために開く会議。
- 閣議
- 33) 内閣のすべての構成員が職を辞めること。衆議院議員総選挙後や内閣不信任決議後などに行われる。
- 総辞職
- 34) 行政を担当する職員。
- 公務員
- 35) 行政の無駄を省き,簡素で効率的な行政をめざす改革。
- 行政改革
- 36) 自由な経済活動をうながすために,行政のもつ許認可権を見直して規制を緩めること。
- 規制緩和
- 37) 三審制において最後の裁判が行われ,東京都だけにある裁判所。
- 最高裁判所
- 38) 日本の裁判所のうち,高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所,簡易裁判所の総称。
- 下級裁判所
- 39) 三審制において,おもに第二審の裁判が行われる裁判所。東京都や名古屋市など,8か所にある。
- 高等裁判所
- 40) 三審制において,おもに第一審の裁判が行われる裁判所。簡易裁判所における民事裁判の判決に不服な場合に,第二審の裁判が行われる裁判所でもある。
- 地方裁判所
- 41) 三審制において,第一審の裁判が行われる裁判所。438か所にある。
- 簡易裁判所
- 42) 第一審判決に不服な場合に,第二審の裁判所に裁判を求めること。
- 控訴
- 43) 第二審判決に不服な場合に,第三審の裁判所に裁判を求めること。
- 上告
- 44) 慎重な裁判で人権を守るため,同じ事件において3段階で裁判を行えるしくみ。
- 三審制
- 45) 裁判官は,外部に干渉されず,自らの良心に従い,憲法と法律にのみ拘束されるという原則。
- 司法権の独立
- 46) 私人の間の争いを扱う裁判。
- 民事裁判
- 47) 犯罪行為を扱う裁判。
- 刑事裁判
- 48) 民事裁判で自分の権利を侵害されたとして,裁判所に訴えた人のこと。
- 原告
- 49) 裁判所に起訴された,犯罪行為が疑われている人。
- 被告人
- 50) 裁判で法にもとづき判決を下す役割を負う人。令状を発する権限ももつ。
- 裁判官
- 51) 刑事裁判で犯罪行為の疑いのある人を裁判所に起訴し,有罪を主張して刑罰を求める役割を負う人。
- 検察官
- 52) 民事裁判の争いの当事者や,刑事裁判で犯罪行為が疑われている人の利益を守る代理人や弁護人として活動する役割を負う人。
- 弁護士
- 53) 身近で利用しやすい裁判制度をめざした改革。
- 司法制度改革
- 54) 重大な犯罪事件を扱う刑事裁判に,国民が裁判官とともに公判に出席して,有罪かどうかや,刑罰の内容を決める制度。
- 裁判員制度
- 55) 検察官が起訴しなかったことのよしあしを審査する機関。抽選された国民で構成される。
- 検察審査会
- 56) 国家権力のうち,国会が担う権力。
- 立法権
- 57) 国家権力のうち,内閣が担う権力。
- 行政権
- 58) 国家権力のうち,裁判所が担う権力。
- 司法権
- 59) 国民の人権を守るために,国の権力を3つの独立した機関に分けるしくみ。
- 三権分立(権力分立)
- 60) 最高裁判所の裁判官を辞めさせるかどうかを国民が投票する制度。
- 国民審査
- 61) 法律や国の行為が憲法に違反していないか,裁判所が審査する制度。
- 違憲審査制
- 62) 地方の政治は,住民の意思にもとづき,国から自立して行われるという原則。「民主主義の学校」といわれる。
- 地方自治
- 63) 地方公共団体独自の活動のため,仕事や財源を国から地方へ移す動き。
- 地方分権
- 64) 地域の住民が直接選挙で選んだ知事や市(区)町村長のこと。
- 首長
- 65) 地域の住民が直接選挙で選んだ議員からなる機関。
- 地方議会(議会)
- 66) 首長と地方議会の議員という,2種類の代表を住民が直接選ぶ制度。
- 二元代表制
- 67) 法律の範囲内で定められる,地方公共団体独自の決まり。
- 条例
- 68) 条例の制定・改廃や議会の解散などを,住民が直接求める権利。
- 直接請求権
- 69) 条例の制定・改廃を求める際に必要な有権者の署名数。(分数で答えなさい。)
- 50分の1以上
- 70) 住民投票によって,知事や市(区)町村長,議員などを辞めさせること。
- リコール
- 71) 地方公共団体が独自に集める税。
- 地方税
- 72) 地方公共団体間の財政格差をなくすために国から交付される財源。
- 地方交付税交付金
- 73) 特定の事業を行うために国から支給される財源。
- 国庫支出金
- 74) 複数の市町村がまとまって1つの地方公共団体になる動き。
- 市町村合併
- 75) 地域の重要課題について,住民の意思を明らかにするために行われる投票。
- 住民投票
- 76) 自発的に社会貢献活動を行うこと。
- ボランティア
- 77) 利益を目的としないで社会貢献活動を行う団体。
- NPO(非営利組織)
④私たちの暮らしと経済
- 1) 収入を得て,必要な支出を行うことで成り立つ,消費生活の単位。
- 家計
- 2) 食料品,住居,衣服,娯楽,教育,医療,通信などにかかる支出。
- 消費支出
- 3) 収入から消費支出と税金や社会保険料などを差し引いた残高で,将来の支出に備えた預金や株式などの財産。
- 貯蓄
- 4) 消費者が,自分の意思と判断で商品を選び,購入する権利をもつこと。
- 消費者主権
- 5) 訪問販売などで商品を購入した場合,一定期間内であれば契約を取り消すことができる制度。
- クーリング・オフ(制度)
- 6) 製品の欠陥によって消費者が被害を受けた場合,製造した企業に過失がなくても,企業に被害の救済を義務づけた法律。
- 製造物責任法(PL法)
- 7) 契約上のトラブルから消費者を守る法律。
- 消費者契約法
- 8) 消費者の権利を明らかにし,企業と国などの責任を定めた法律。
- 消費者基本法
- 9) 消費者行政を一元化するために,2009年に設置された,国の行政機関。
- 消費者庁
- 10) 生産された商品が消費者に届くまでの流れ。
- (商品の)流通
- 11) 商品を,卸売業者から仕入れるなどして,消費者に売る業者。
- 小売業者
- 12) 商品が生産者から消費者に届くまでの流れを,より効率化すること。
- 流通の合理化
- 13) 企業が資本をもとに,利潤を目的として,生産活動を行う経済。
- 資本主義経済
- 14) 利潤を目的とする企業。
- 私企業(民間企業)
- 15) 利潤を目的としない企業。
- 公企業
- 16) 独自の先進技術やアイデアにもとづき起業し,革新的な事業を展開する中小企業。
- ベンチャー企業
- 17) 株式会社が資金を集めるために発行するもの。
- 株式
- 18) 株主が株式会社から受け取る,利潤の一部。
- 配当
- 19) 株式会社が経営方針などを議決するために行う会議。株主が議決権をもつ。
- 株主総会
- 20) 労働条件の最低基準を定めた法律。
- 労働基準法
- 21) 労働者が労働組合を結成することなどを定めた法律。
- 労働組合法
- 22) 労働争議を予防・解決するための法律。
- 労働関係調整法
- 23) 仕事と,家庭や地域における生活とが調和した状態。
- ワーク・ライフ・バランス
- 24) アルバイト,パート,派遣労働者,契約労働者など,正社員以外の労働者。
- 非正規労働者(非正社員)
- 25) 社会のすみずみまで市場がはりめぐらされている経済。
- 市場経済
- 26) 価格を見て,消費者が買おうとする量。
- 需要量
- 27) 価格を見て,生産者が売ろうとする量。
- 供給量
- 28) 需要量と供給量が一致する時の価格。
- 均衡価格
- 29) 1社の企業により,生産や販売市場が支配されていること。
- 独占
- 30) 少数の企業により,生産や販売市場が支配されていること。
- 寡占
- 31) 1社の企業が市場を支配し,価格競争が弱まっている状態で決められる価格。
- 独占価格
- 32) 企業の市場での公正で自由な競争をうながし,消費者の利益を守るための法律。
- 独占禁止法
- 33) 独占禁止法を運用するための機関。
- 公正取引委員会
- 34) 国や地方公共団体が決定・認可などを行う,水道・鉄道・乗合バスなどの公共性の高いサービスの料金。
- 公共料金
- 35) 貸し手と借り手が直接お金を融通する,金融の方法。
- 直接金融
- 36) 金融機関を仲立ちとしてお金を融通する,金融の方法。
- 間接金融
- 37) お金の借り手が貸し手に対して,元金を返済するほかに支払うお金。
- 利子(利息)
- 38) 日本の中央銀行。
- 日本銀行(日銀)
- 39) 日本銀行券(紙幣)を発行する日本銀行の役割。
- 発券銀行
- 40) 政府の資金を扱う日本銀行の役割。
- 政府の銀行
- 41) 一般の銀行に資金の貸し出しをする日本銀行の役割。
- 銀行の銀行
- 42) ものが売れるようになる,生産の増加など,経済が活発化すること。
- 好景気(好況)
- 43) ものが売れなくなる,生産の減少など,経済が落ち込むこと。
- 不景気(不況)
- 44) 物価が上昇し続けること。
- インフレーション
- 45) 物価が下落し続けること。
- デフレーション
- 46) 中央銀行が,銀行の資金量を増減させて,銀行の貸し出し量を操作し,物価や景気に影響をあたえようとする政策。
- 金融政策
- 47) 1980年代後半に起こり,1991年に崩壊した,地価や株価が経済の実態をこえて,異常に高くなった経済。
- バブル経済
- 48) 異なる通貨の交換比率。
- 為替相場(為替レート)
- 49) 円の価値が,他の通貨に対して上がること。
- 円高
- 50) 円の価値が,他の通貨に対して下がること。
- 円安
- 51) 海外に現地籍の企業をつくるなど,世界規模で活動する企業。
- 多国籍企業
- 52) 政府が予算にもとづいて,収入を得て,支出をする活動。
- 財政
- 53) 国に納める税金。
- 国税
- 54) 納税者と担税者が一致する税金。
- 直接税
- 55) 納税者と担税者が異なる税金。
- 間接税
- 56) 所得に対してかけられる税金。
- 所得税
- 57) 消費に対してかけられる税金。
- 消費税
- 58) 所得が多くなるにしたがって税率を高くする課税方法。
- 累進課税
- 59) 政府のおもな財源。家計や企業が納める。
- 税金(租税)
- 60) 政府が提供する,社会保障などのサービス。
- 公共サービス
- 61) 政府が供給する教育施設や道路・港湾などの施設。
- 社会資本(インフラ)
- 62) 政府が,減税や増税,公共投資の増減などによって景気を調節する政策。
- 財政政策
- 63) 国が,税収の不足を補うために発行する債券。
- 国債
- 64) 地方公共団体が,税収の不足を補うために発行する債券。
- 地方債
- 65) 病気や老齢などで生活が困難になった時,国が個人の生活を保障する考え方。
- 社会保障
- 66) 日本の社会保障制度のうち,医療保険,年金保険,雇用保険,労災保険などのこと。
- 社会保険
- 67) 日本の社会保障制度のうち,生活保護(生活扶助・住宅扶助・教育扶助など)のこと。
- 公的扶助
- 68) 日本の社会保障制度のうち,高齢者・障がいのある人たち・児童への福祉などのこと。
- 社会福祉
- 69) 日本の社会保障制度のうち,感染症対策,上下水道整備,公害対策などのこと。
- 公衆衛生
- 70) 介護が必要となった場合に,費用を部分的に負担して介護サービスを受けることができる制度。
- 介護保険(制度)
- 71) 企業の生産活動や人々の日常生活から生じる大気汚染や水質汚濁などによって,人々の健康や生活環境が損なわれること。
- 公害
- 72) 熊本県で発生した,水質汚濁を原因とする公害病。
- 水俣病
- 73) 新潟県で発生した,水質汚濁を原因とする公害病。
- 新潟水俣病
- 74) 富山県神通川流域が被害地域となった,水質汚濁を原因とする公害病。
- イタイイタイ病
- 75) 三重県四日市市が被害地域となった,大気汚染を原因とする公害病。
- 四日市ぜんそく
- 76) 公害対策基本法を発展させて制定された,環境政策の基本となる法律。
- 環境基本法
- 77) 廃棄物を再生利用すること。
- リサイクル
- 78) 資源を有効に使い回して,廃棄物を最小限におさえる社会。
- 循環型社会
⑤地球社会と私たち
- 1) 他国の支配や干渉を受けず,平等に扱われる権利をもつ国。
- 主権国家
- 2) 国家の領域のうち,陸地の部分。
- 領土
- 3) 国家の領域のうち,大気圏内の空の部分。
- 領空
- 4) 国家の領域の周辺で,領土沿岸から200海里以内の水域。
- 排他的経済水域
- 5) 条約や,慣行をもとにした法などの,国際社会における決まり。
- 国際法
- 6) 日本政府が,ロシアが不法に占拠しているとして返還を求めている,日本固有の領土。
- 北方領土
- 7) 世界の平和と安全の維持を目的として,強い権限をもつ国連の主要機関。
- 安全保障理事会(安保理)
- 8) 国連安保理の常任理事国が1か国でも反対すると決議を採択できないという権限。
- 拒否権
- 9) 国連が,紛争地域などで行う停戦の監視や選挙の監視などの活動。
- 平和維持活動(PKO)
- 10) 1993年に発足し,ヨーロッパの多くの国が加盟する,市場統合などを進める組織。
- ヨーロッパ連合(EU)
- 11) 1967年,東南アジアの国々が地域内の安定と発展を求めて,経済や政治などの分野で協力を進めるために設立した組織。
- 東南アジア諸国連合(ASEAN)
- 12) 発展途上国と先進工業国の間の経済格差と,そこから発生する諸問題。
- 南北問題
- 13) 温室効果ガスの増加にともない,地球の気温が上昇する現象。
- 地球温暖化
- 14) 1997年に開かれた地球温暖化防止京都会議で採択された,先進工業国に温室効果ガスの排出削減を義務づけた文書。
- 京都議定書
- 15) 石油,石炭,天然ガスなどのエネルギー資源。
- 化石燃料
- 16) 太陽光,風力などの環境への負荷が少ないクリーンなエネルギー。
- 再生可能エネルギー
- 17) 発展途上国の人々が生産した製品を,労働に見合った価格で取り引きすることで,人々の生活を支える取り組み。
- フェアトレード(公正貿易)
- 18) 政治的な事情や,迫害,紛争などにより,祖国から逃れた人。
- 難民
- 19) 特定の集団が,政治的目的を達成するために,敵対する国の軍隊や一般の人々を無差別に攻撃する行為。
- テロリズム(テロ)
- 20) 資金援助や技術協力などの,発展途上国に対する政府の経済協力。
- 政府開発援助(ODA)
- 21) 非核保有国が新たに核兵器を持つことを禁止した条約。
- 核拡散防止条約
- 22) 一人ひとりの人間の生命や人権を紛争や貧困などの脅威から守り,各個人がもつ豊かな可能性を実現できるようにしようという考え方。
- 人間の安全保障