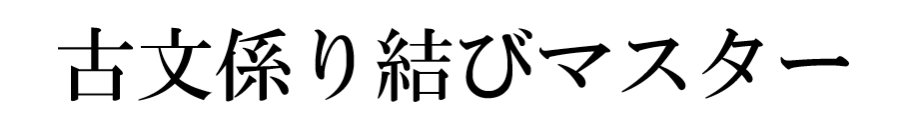係 り結びの法則とはどんな法則か
人、
「榎木(えのきの)僧正(そうじやう)」とぞ言
ひけ
る。
(中略)
~ 「きりくひの僧正」と言ひけ
り。
(中略)
~「 堀池(ほりけ)の僧正」とぞ言
ひけ
る。
本 文を何回か音読すればすぐに気づけると思いますが、
本
文中に「ぞ」が入ると文末が「ける」になり、
本
文中に「ぞ」がないと文末が「けり」になります。
こ のように文 中に「ぞ」のような特殊な言葉が入ると、文末の表現が影響を受けて形を変えてしまうことを「係り結びの法則」と言います。
ま
た、文末の形を変えてしまう「ぞ」
のような言葉を「係助詞(かかりじょし)」と言います。
係助詞は「ぞ」以外にもいくつかありますので、文末の形との関係を表にまとめておきます。
①
文中に「係助詞」と呼ばれる特殊な言葉が入ると、文末が形を変えてしまう法則。
②係助詞の「や」「か」は特別な意味を持ち、訳し方に注意する必要がある。
| 係 助詞 | 文 末の形 | 意 味と訳 |
|---|---|---|
| ぞ・ なむ | 連 体形 | 強 意「~だなぁ」 |
| や・ か | 連 体形 | 疑
問「~だろうか」 反語「~だろうか、いや~ではない」 |
| こ そ | 已 然形(いぜんけい) | 強 意「~だなぁ」 |
ち なみに係 助詞がない場合の文末の形は「終止形」になります。
連 体形、已然形ってなに?と思う人が多いかと思いますが、ここは高校でやるところなので、ざっくりと、連 体形はウ段が多い、已然形はエ段が多いと覚えておいてくれればOK。
ち
なみに、
・
連体形…後ろに「とき」「こと」などの名詞をつけたときの形
・已然形…後ろに「ども」をつけたときの形
と
なります。
【超 重要】疑問と反語の訳し方を覚える
係
助詞の「や」「か」が文中に入った場合の訳し方は超重要です。
高校入試でも難関高校になるとここの訳を答えさせますし、大学入試では必ず通過しないといけない基本ポイントです。
1.
原則
本文中の「や」「か」が疑問か反語のどちらで訳すかは文章の流れから読み手が判断する。
2.
疑問で訳すことが多い場合
文中に「~
にや」「~
にか」と「に」とセットで使われた場合は疑
問で訳すことが多い。
疑問は「~
だろうか。」と訳すのが基本。
3.反語で訳すことが多い場合
文中に「~
やは」「~
かは」と「は」とセットで使われた場合は反
語で訳すことが多い。
反語は「~
だろうか、いや~ではない。」と訳すのが基本。
試 しに例文を訳してみましょう。
【例
文①】大きなる人にやあ
らん。
⇒大きな人だ
ろうか。
【例
文②】何か
は苦しき。
⇒何か苦しいのだ
ろうか、いや苦しくはな
いだろう。
【例
文③】花は盛りに見るものか
は。(結びが省略されています)
⇒花は盛りの(満開の)ときに見るものだ
ろうか、いやそうではな
いだろう。
係り結び 練習問題 次の各文を現代語に訳しなさい
六野太を馬の上で二刀、落ち着くところで一刀、三刀までぞ突かれた る。(平家物語)
『六野太を馬の上で二回刀で突き、馬から落ちたところで一回、合わせて三回も突いた。』
あかずやありけん、二十日の、夜の月出づるまでぞありけ り。(土佐日記)
『まだ満足できなかったのであろうか。二十日の夜の月が出るまでそこにいたのです。』
人あまたあれど、一人に向きて言ふを、おのづから人も聞くにこそあれ。 (徒然草)
『人が多くいても、一人に向かって言うのを、自然と他の人も聞くものだ。』
ここにても、人は見るまじうやは。などかはさしもうち解けつる」と笑 はせたまふ。(枕草子)
『ここでも、人が見ていないとは限りません。どうしてそのように気を許したのですか。』
飼ひける犬の暗けれど主を知りて、飛びつきたるけるとぞいふ。(徒然草)
『飼っていた犬が暗かったけれども飼い主を見分けて、飛びついたということである、と言う。』
乾き砂子の用意やはなかりけり。 (徒然草)
『乾いた砂の用意はなかったのだろうか。』
よき人は、知りたる事とて、さのみ知り顔にやは言ふ。(徒然草)
『優れた人は、自分が知っていることだからといって、そんなに知り顔で言うであろうか(言わない)。』
ひがごとせんとてまかる者なれば、いづくをか、刈らざらむ(徒 然草)
『間違ったことをしようとして出かけるものなので、どこの(田を)刈らないことがあろうか(どこでも刈るのだ)。』
呼 応の副詞
呼
応の副詞と
は、下にくる特定の語とセットになって働く副詞のことです。
呼応の副詞には、次のようなものがあります。
「え さらず」「えならず」「えもいはず」などという形で慣用表現になっていることも多いです ね。「えさらず」は「え 避らず」で「避けることができない」。「え ならず」「え 避らず」に 共通するのは「す ばらしい」と いうこと。
「え 成らず」で実現不可能なぐらい素晴らしい、「えも言はず」は言葉にできないことです。ただ、こちらは、悪いことにも使いますね。言葉 にできないぐらいひどい、ということです。
「まっ
たく、少しも~ない」の意味を表す呼応の副詞は
さまざまなパターンがありますが、まずは
つ
ゆ~打消
をおぼえましょう。
他 にも、
「え ~ じ(ず)」で「できない」。
「つ ゆ ~ ず」で「まったく~ない」。
「よ
も ~ じ」で「まさか~ないだろう」。
「な~ そ」で「するな」。「い
かがは~む」で疑問・反語。
は よく出題されるので覚えておきましょう。

呼応の副詞
この玉はたやすくえ取らじ
この玉はたやすく取ることはできまい
涙な添へそ
涙を添えさせないでくれ
つゆ知らず
少しも知らない
今はよも鳥にとられじ。
今となってはまさか鳥に取られることもないだ ろう
神鳴る音で、え聞かざりけ リ
雷が鳴る音で、聞くことができなかった
や、な起こしてたてまつりぞ
おい、起こし申し上げるな
かの国の人、来なば、猛き心つかふ人も、よもあらじ
あの国の人が、来たならば、勇ましい心で立ち向かう人も、まさかいな いだろう
いとにくく腹立たしけれども、いかがはせむ
しゃくにさわって腹立たしいけれども、どうしようか、いや、どうにもならない。
酒宴ことさめて、いかがはせむと 惑ひけり
酒宴は興ざめになって、どうしようかと途方に暮れた。